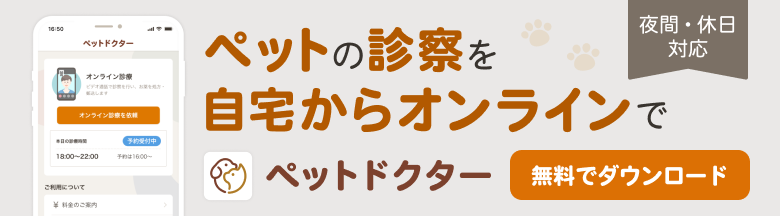2025年10月9日

秋は夏の疲れがどっと出たり、寒暖差に体がついていけなかったりすることで、犬も体調を崩しやすい時期です。この記事では秋に犬が発症しやすい病気や症状のサイン、愛犬の健康を守るために飼い主ができる予防対策を解説します。
愛犬の秋の体調不良に注意しよう
秋は涼しくて犬にとって過ごしやすい季節ですが、寒暖差や気圧の変動で自律神経が乱れて免疫力が低下し、様々な病気にかかりやすくなる時期でもあります。
夏の疲れがどっと出ることもあり、特にシニア犬や持病のある犬は体調不良に注意が必要です。愛犬の様子を注意深く観察し、病気のサインを見逃さないようにしましょう。
犬が秋に発症しやすい病気と見逃せないサイン
それではここから、秋の寒暖差や環境の変化が引き金となりやすい病気と、その具体的な症状、サインを解説します。気になる症状が見られる場合は早めに動物病院を受診すると安心です。
呼吸器系の病気(風邪、気管支炎など)
朝晩の冷え込みや寒暖差、暖房を使い始めることによる空気の乾燥などで喉や気管支の粘膜が弱り、風邪や気管支炎の症状が出ることがあります。
症状やサイン
- 咳やくしゃみ、鼻水が続く
- なんとなく元気がない、食欲が落ちる
- 目やにが増える
- 鼻が乾く
- 喉に何かが詰まったような「カッカッ」という咳をする
- 呼吸が荒くなる
消化器系の病気(腹痛、嘔吐、下痢など)
夏の疲れが残るなかでの寒暖差による自律神経の乱れや、急な冷えこみによるお腹の冷え、夏の間落ちていた食欲が回復することによる急な食べすぎなどが原因で、お腹の症状が出ることもあります。
症状やサイン
- 下痢や軟便が続く
- 便秘が続く
- 嘔吐する
- お腹を丸めている、お腹を触ると嫌がる
- 食欲が大幅に落ちる、または急に食欲が増えすぎる
泌尿器の病気(膀胱炎、尿石症など)
秋になると水を飲む量が自然と減るため、尿が濃くなり、細菌の繁殖や結石のリスクが高まります。
症状やサイン
- おしっこに行く回数が増える(頻尿)
- おしっこが少量しか出ない、出にくい(排尿困難)
- おしっこのときにクーンと鳴いたり、ソワソワしたり、背中を丸めたりする
- おしっこに血液が混ざる
- トイレではない場所で粗相をすることが増える
マダニ感染症
マダニ感染症とは、マダニが犬の血を吸う際に、病原体を犬の体内へ送り込むことで発症する病気の総称です。場合によっては、重症化して命に関わる危険性もあります。
マダニは公園の草むらなどに生息していて、春と秋に最も活発に活動するため、秋は特に注意が必要です。
症状やサイン
- 散歩や外出後に皮膚(頭、顔、耳などが多い)に黒いイボのようなもの(マダニ)が食いついている
- 発熱、食欲不振、元気がなくなる
もしマダニが付着しているのを発見したら、すぐ動物病院を受診して専用器具を使って除去してもらいましょう。自分で取ろうと無理に引っ張ると、マダニの口元が皮膚に残り、炎症を起こす危険性があります。
アレルギー性皮膚炎
秋に飛散するブタクサ、ヨモギなどの花粉や、夏に繁殖したダニの死骸やフンがアレルゲンとなり、皮膚炎が悪化することがあります。
症状やサイン
- 体を執拗に掻く、舐め続ける
- 皮膚に赤みや小さなブツブツが見られる
- 部分的に脱毛している
- 耳を頻繁に掻く、耳が赤い、熱を持っている
関節や古傷の痛み
寒暖差や気圧の変化で血行が悪くなり、関節や古傷の痛みが悪化することがあります。
症状やサイン
- 散歩を嫌がる、いつもより歩くのが遅い
- 動き出しがぎこちない、特に寝起きや朝の動きが鈍い
- 階段や段差の上り下りをためらう
- 患部を触ると嫌がる、唸る
犬の秋の病気を予防するには?飼い主ができる対策
秋の病気を防ぐためには、日々の生活の中で寒暖差に対処したり、免疫力の低下を防いだりといった対策が欠かせません。ここからは秋に愛犬が元気に過ごせるように飼い主ができる対策をご紹介します。
1. 寒暖差と乾燥を防ぐ環境を整える
まず大切なのは、愛犬が過ごす室内の環境を整えることです。呼吸器系の病気や関節痛、免疫力低下を防ぐことにつながります。
・室内の温度を安定させる
エアコンなどを活用し、犬が過ごす部屋の温度を日中と夜間で大きく変えないように調整しましょう。
・湿度を管理する
秋は空気が乾燥するので、加湿器などを使って40~60%程度の湿度を保てるようにしましょう。乾燥すると喉や気管支の粘膜が弱って風邪のリスクが高まるほか、皮膚炎の痒みが悪化する原因にもなります。
・暖かい寝床を用意する
冷えた床の上に寝ていると、体が冷えて関節痛の悪化につながります。愛犬の寝床に暖かいブランケットやベッドを用意して、暖かく過ごせる場所を確保してあげましょう。
2. 栄養と水分をしっかり摂らせる
栄養はどの季節でも大切なことですが、秋は特に食べ過ぎや消化器系の不調に注意した食べさせ方ができるといいでしょう。また涼しくなると水を飲む量が減りがちなので、意識的に水分を摂らせてあげてください。消化器系や泌尿器系の病気予防や、免疫力のサポートに繋がります。
・水分補給を徹底する
涼しくなって飲水量が減ると、尿が濃縮して膀胱炎や尿結石のリスクが高まります。水飲み場を複数用意したり、容器の素材を気に入るものに変えたり、普段の食事にウェットフードを混ぜたりして、意識的に水分補給を促しましょう。
・消化に優しい食事を与える
秋バテによる消化器系の不調がある場合は、ウェットフードなど消化の良い食事を与えましょう。逆に涼しくなって食欲が回復したという場合は、急激な食べすぎを防ぐために食事量を調整し、胃腸への負担を減らしましょう。
3. 散歩や日常で、安全と衛生を管理する
アレルギーやマダニ感染といった外側からのリスクを防ぐために、日常生活の中で安全や衛生管理につとめましょう。
・マダニ予防薬を投与する
秋はマダニの活動がピークを迎えるため、獣医師に相談の上、マダニの予防薬を忘れずに投与しましょう。これが最も確実なマダニ感染症の予防方法です。
・散歩後に体を拭く
秋の花粉やマダニの付着を防ぐために、散歩後は体や足を濡れたタオルなどでいつもより丁寧に拭き取りましょう。特にアレルギーのある犬には必須の対策です。玄関先でブラッシングをしてあげてもいいでしょう。
・草むらでの散歩を避ける
秋は草むらでの散歩を避けるのが安心です。ブタクサやヨモギといった秋花粉は身近な草むらに生えていますし、マダニも草むらに生息しています。
愛犬の健康に関する相談はオンラインでも
愛犬に元気がなかったり、不調があるように感じたりすると、動物病院を受診すべきか判断に迷うこともあるかと思います。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話で獣医師と繋がり、オンラインで診察を受けることができます。獣医師が必要と判断した場合はお薬を処方してもらうことも可能です。通院の手間がかからないので、困ったときは検討してみてくださいね。