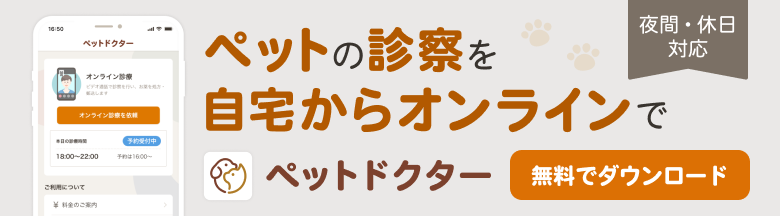2025年10月10日

秋は涼しくて犬にとっても過ごしやすい季節ですが、夏の疲れや急な寒暖差などで体調が崩れやすかったり、散歩時に危険が多かったりするタイミングでもあります。そこでこの記事では、愛犬の健康を守るために秋に特に注意すべき11のポイントを解説します。
犬が秋に気をつけたいこと① 秋に発症しやすい病気
秋は、夏の疲労による免疫力の低下や、寒暖差による自律神経の乱れ、空気の乾燥などが原因で病気にかかりやすくなります。以下のような病気に注意が必要です。
呼吸器系の病気
朝晩の冷え込みや乾燥が原因で起こります。咳やくしゃみ、鼻水、目の充血が続く場合や、喉に何かが詰まったような「カッカッ」という咳をする場合は、動物病院を受診しましょう。
消化器系の不調
夏の疲れや自律神経の乱れ、急な冷え込みでお腹を壊し、下痢や嘔吐が見られることがあります。消化の良い食事と水分を与え、必要に応じて動物病院を受診しましょう。
秋の病気を予防するためには、日頃から寒暖差や乾燥対策を行い、水分や食事をしっかり摂らせることが大切です。あとの章で詳しく解説するので参考にしてくださいね。
犬が秋に気をつけたいこと② 秋のアレルギー
秋に飛散するブタクサやヨモギといった花粉や、室内のダニの死骸などが原因で、秋はアレルギー症状が悪化することがあります。体を執拗に掻いたり舐めるほか、皮膚に赤みや発疹が出た場合は、アレルギーを疑いましょう。
アレルギー対策の基本は、アレルギーの原因(アレルゲン)に触れさせないことです。花粉を連れて帰ってこないように散歩後は全身を濡れたタオルで拭いてあげたり、室内のアレルゲンを除去するためにこまめに掃除機をかけたりしましょう。症状がひどい場合は動物病院を受診してください。
犬が秋に気をつけたいこと③ 関節痛
特にシニア犬や持病を持つ犬は、秋の寒暖差や気圧の変化で血行が悪くなり、関節に痛みを感じやすくなります。
散歩や階段の上り下りを嫌がる、寝起きや朝の動きがぎこちない、関節の近くを触ると唸るといった様子が見られるときは、関節を痛めているサインかもしれません。一度動物病院を受診すると安心ですよ。
関節痛を予防するにはこのあとご紹介する寒暖差対策が有効なので、あわせて参考にしてください。
犬が秋に気をつけたいこと④ 寒暖差
秋は夏が終わって急に涼しくなったり、朝晩は冷えるのに日中は暑かったりと、寒暖差が激しくなります。すると体温調節を司る自律神経に負担がかかってバランスが乱れ、免疫力が低下するほか、体が冷えると体調を崩しやすくなります。
そのため秋はエアコンなどを活用し、室内温度を日中と夜間で大きく変えないように安定させましょう。愛犬の寝床にあたたかいベッドやブランケットを置いたり、お気に入りの場所にカーペットを敷いたりと、体が冷えないような対策を行うことも大切です。
犬が秋に気をつけたいこと⑤ 乾燥
秋になると湿度が低下し、空気が乾燥しはじめます。空気が乾燥すると喉や気管支の粘膜が乾燥して風邪のリスクが高まるほか、皮膚のバリア機能が低下してフケやかゆみが出やすくなります。加湿器を使用したり、洗濯物を室内に干したりして、意識的に加湿しましょう。
犬が快適に過ごせる湿度は40〜60%と言われています。
犬が秋に気をつけたいこと⑥ 換毛期
秋になると、ダブルコートの犬は冬に備えて「換毛期(毛の生え変わり時期)」をむかえます。
換毛期には抜け毛が増えますが、放置すると皮膚病や毛玉の原因になります。抜け毛が多くなってきたらできるだけ毎日ブラッシングを行いましょう。皮膚の血行が促進され、健康な冬毛の成長を促すことができます。
犬が秋に気をつけたいこと⑦ マダニ
マダニは命に関わる病気を媒介する危険な害虫です。春と秋に活動が活発化するため、秋になったらマダニ予防薬を投与しておくと安心ですよ。
またマダニは草むらに生息しているので、散歩やアウトドアの際は草むらに近寄らないようにしましょう。散歩後は全身をチェックし、特に耳や足、顔周りにマダニがついていないか確認してください。
もし愛犬の体にマダニがついているのを発見したら、自分で取ろうとせず動物病院を受診しましょう。無理に取るとマダニの口元だけが犬の体に残ってしまう危険性があります。
犬が秋に気をつけたいこと⑧ 水分補給
涼しくなると自然と水を飲む量が減ってしまいます。水分補給は健康維持の基本ですし、水分が不足すると膀胱炎や尿結石といった泌尿器系の病気のリスクが高まるため、意識的に水を飲ませる工夫をしましょう。
たとえば水飲み場を増やしたり、なかなか飲みたがらない場合は普段の食事にウェットフードを混ぜたりしてもいいでしょう。水を少し温めてぬるま湯にすると飲みやすくなることもあります。
犬が秋に気をつけたいこと⑨ 食べ過ぎ
夏バテで食欲が落ちていた犬が、涼しくなって急に食欲を取り戻すことがあります。栄養をしっかり摂ることは大切ですが、食べ過ぎると肥満のリスクが高まります。また急な食べ過ぎは消化器系に負担をかけ、嘔吐や下痢の原因にもなり得るので、急に大量のフードを与えないようにしてください。
体調や体重を見ながらフードの量を少しずつ調整できるといいですね。
犬が秋に気をつけたいこと⑩ 拾い食い
秋になると、散歩道にキノコやどんぐり、銀杏、もみじなどが落ちていることがあります。これらを散歩中に愛犬が拾い食いしないように十分注意してください。食べてしまうと、中毒や内臓の損傷につながる可能性があります。
散歩中は常に愛犬から目を離さないようにして、拾い食いをさせないようにリードを短く持ちましょう。紅葉の中をお散歩するのは控えたほうが安心です。拾い食いしてしまった場合は、ただちに動物病院を受診してください。
犬が秋に気をつけたいこと⑪ 台風や雷
秋は台風や悪天候が多い季節ですが、犬はこれらが苦手です。雷の音や光、強風や急な天候の変化に恐怖を感じ、不安やパニックに陥ることがあります。
飼い主が落ち着いている様子を見ることで犬も落ち着くことがあるので、まずはいつも通りに過ごすことが大切です。あまりにも怖がる場合は、カーテンや雨戸を閉めて安心して過ごせる場所を作ってあげましょう。優しく撫でたり声をかけたりして安心させてあげるのも効果的です。
犬の健康に関する相談はオンラインでも
秋は犬にちょっとした不調や異変が現れやすいタイミングです。愛犬の様子がいつもと違うと、動物病院を受診したほうがいいか迷うこともあるかもしれませんね。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話で獣医師と繋がり、愛犬の様子を見せながら診察を受けることができます。獣医師が必要と判断した場合は薬も処方してもらえます。心配なときは利用を検討してみてくださいね。