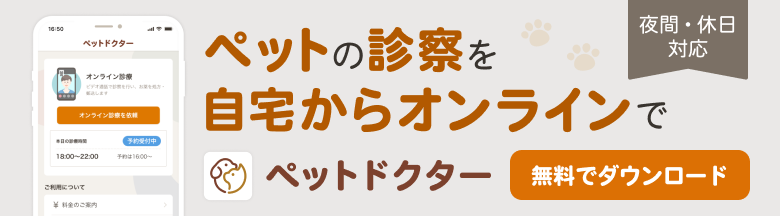2025年10月9日

夏が終わって涼しくなっても、愛猫がぐったりしている、遊びに誘っても反応が鈍い…もしかしたら「秋バテ」かもしれません。この記事では、猫が秋バテになる原因と症状、家庭でできる対策や受診の目安を解説します。
猫の「秋バテ」って何?原因は?
夏が終わって涼しくなった秋口に起こる、元気がない、食欲がないなどちょっとした不調のことを「秋バテ」といいます。正式な医学用語ではありませんが、多くの人や猫が体感しているものです。
猫の秋バテは、主に以下の3つの要因が重なることで起こります。
自律神経の乱れ
猫は人間よりも体温調節が苦手です。そのため夏の暑い間は、体温を一定に保つ役割を担う「自律神経」が酷使され、交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経が乱れると免疫力や回復力の低下につながり、体調不良を起こしやすくなります。
寒暖差や気圧差
秋は1日の中での寒暖差が激しくなります。ここでも、朝晩の冷え込みに自律神経が対応しきれず、バランスの乱れが起こりがちです。人間と同様に気圧の変化も体に負担をかけ、体調不良につながることがあります。
夏の疲労の蓄積
夏は暑くて疲労が溜まりがちです。さらに暑さで食欲が減退したり、睡眠が浅くなったりしていると、体力が落ちている可能性もあります。この疲労の蓄積が秋になって表面化し、体調を崩すことがあります。
猫の秋バテの主な症状
猫の秋バテでは、以下のような症状が見られることが多いです。猫は体調不良を隠そうとするので、注意深く観察してあげてください。
- 寝ている時間が増えて活動量が低下する
- 遊びへの反応が鈍くなる、高い場所に飛び乗るのをためらう
- 食欲が減退する、 ごはんを残す
- 毛づくろいが雑になり毛並みがパサつく、逆に過剰に舐め続ける
- 便が緩くなる、または逆に便秘気味になる
ただし上記のような症状は、秋バテではなく病気が原因で起こっている可能性があります。次の章でご紹介する受診目安を参考に、必要な場合は動物病院を受診してください。
単なる秋バテではないかも?こんなときは動物病院へ
以下のようなサインが見られた場合は、単なる秋バテではなく別の病気が隠れている可能性があります。速やかに動物病院を受診しましょう。
- 24時間以上、全く食欲がない
- 水を飲まない
- 便秘が続いている
- 頻繁に嘔吐している、連続で嘔吐している
- 体重が急激に減っている
- 耳が熱い、体が冷たいなど体温に異常がある
- ぐったりしていて意識がはっきりしない
このような症状がなくても、秋バテの症状が長引いているときや心配なときは、早めに動物病院を受診すると安心です。
愛猫の秋バテを解消するために自宅でできる対処法
秋バテは一時的なものではありますが、愛猫にはできるだけ早く元気になってほしいものです。以下のようなケアを自宅で行い、回復をサポートしてあげられるといいですね。
食べやすいように食事を工夫する
食欲がなく便が緩い場合は、消化の良いウェットフードを食事に混ぜると食べやすくなります。胃腸の調子は悪くないものの食欲が無さそうというときは、いつものフードを少し温めると香りが立ち、食欲が刺激されることもあります。
水分補給を促す
涼しくなると飲水量が減りがちです。水分不足になるとさらに体調が悪くなる可能性があるほか、腎臓にも負担がかかってしまうので、部屋の複数箇所に水飲み場を設置するなどしていつでも新鮮な水が飲める状態を保ってあげましょう。猫がよく通る場所やお気に入りの場所に置くと飲みやすくなります。
寒い日は水を少し温めてぬるま湯にしてあげると、好んで飲むこともあります。
寒暖差をなくす
秋は寒暖差が激しいので、エアコンなどを活用して室内の温度をできるだけ一定に保ってあげましょう。特に猫が寝ている場所の温度には気を配ってください。朝晩の冷え込みで体が冷えないように、暖かいベッドなどを用意してあげるのもいいでしょう。
十分に休ませる
無理に遊びに誘ったりかまったりせず、愛猫が望むだけゆっくり休ませてあげましょう。静かに休める場所を作ってあげることも大切です。
体力が回復してきたら、猫じゃらしや知育玩具を使った好奇心を刺激する遊びを短時間取り入れるのもいいでしょう。
優しくスキンシップをとる
自律神経の調子を整えるには、リラックスしたりストレスを解消したりすることも大切です。愛猫が落ち着いているときに優しくマッサージしてあげたり、撫でてあげたりしてください。
秋は換毛期なので、毛が抜けやすい猫には優しくブラッシングしてあげるのもいいですね。
猫の秋バテの相談はオンラインでも
秋に愛猫に元気がないと、秋バテ?それとも病気?と判断に迷うことがあるかもしれません。特に猫は不調を隠すため、食欲不振などが続くと心配になりますよね。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話で獣医師と繋がり、愛猫の様子を見せながら診察を受けることができます。猫は外出や対面受診を嫌がることも多いので、自宅で受診できると安心ですね。困ったときはぜひ検討してみてください。