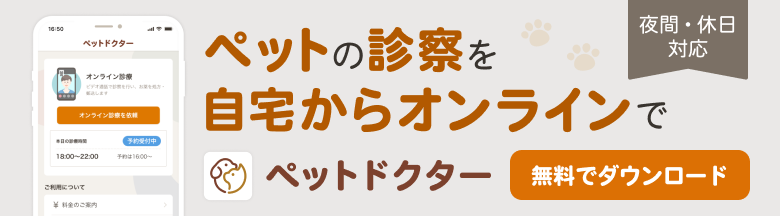2025年10月10日

秋は夏の疲れや寒暖差で猫も体調を崩しやすい季節です。この記事では秋の寒暖差や環境変化によって猫が発症・悪化しやすい具体的な病気のサインと、愛猫の健康を守るために飼い主さんができる予防対策を解説します。
愛猫の秋の体調不良に注意しよう
秋は1日の中での寒暖差が大きくなります。すると猫の体は体温を一定に保とうとして自律神経が過剰に働き、バランスが乱れがちになります。
自律神経のバランスが乱れると、体の回復や免疫を担う機能が低下します。その結果普段よりも不調に弱くなり、様々な病気を発症しやすくなります。
また暖房を使い始めることで空気が乾燥したり、涼しくなることで飲水量が減ったりすることも、病気を引き起こしやすくなります。
猫が秋に発症しやすい病気と見逃せないサイン
それではここから、秋の寒暖差や環境の変化が引き金となりやすい猫の病気とその具体的なサインを解説します。猫は体調不良を隠そうとする性質があるので日頃から様子をよく観察し、異変に気づけるようにしましょう。
1. 呼吸器系の病気(猫風邪など)
朝晩の冷え込みや寒暖差による自律神経の乱れ、暖房を使い始めることによる空気の乾燥で、鼻や喉の粘膜が弱り、風邪などの呼吸器系の病気が起こりやすくなります。
症状やサイン
- くしゃみや鼻水、咳が続く
- 鼻詰まりで口呼吸をする
- 目ヤニが増える、涙が出る
- まぶたが腫れる
- なんとなく元気がない、食欲が低下している
2. 消化器系の不調(腹痛、下痢、嘔吐など)
夏の疲れによる自律神経の乱れや、気温が下がることでの冷え込み、換毛期に伴う毛玉の増加が、お腹を壊す原因となります。
症状やサイン
- 下痢や軟便が続く
- 便秘、毛玉の頻繁な吐き戻し
- お腹を丸めている、お腹を触ると嫌がる
- 食欲が大幅に落ちる、または急に食欲が増えすぎる
- 体重が急に減少する
3. 泌尿器系の病気(膀胱炎、尿石症など)
涼しくなると自然と飲水量が減るため、尿が濃縮し、細菌の繁殖による膀胱炎や尿石症(結石)のリスクが高まります。
症状やサイン
- トイレの回数が増える(頻尿)
- 長時間トイレにこもる
- おしっこに血液が混ざる(血尿)
- トイレではない場所で粗相をすることが増える
- 排尿時に鳴くなど、痛そうな様子が見られる
- おしっこの量が極端に少ない、または全く出ていない
4. 腎臓病
秋になり飲水量が減ると腎臓にも負担がかかります。猫はもともと腎臓病になりやすいため、特に高齢の猫は注意が必要です。
症状やサイン
- 水を飲む量が以前より明らかに増えた
- おしっこの量が増えた
- 食欲不振や嘔吐が見られる
- 口臭がする
- 毛づやが悪くなった、痩せてきた
5.毛球症(ヘアボール)
秋は猫の換毛期で抜け毛が増えるため、グルーミングで飲み込む毛の量も増えます。すると胃や腸で飲み込んだ毛が絡まり、消化器系の閉塞を引き起こすことがあります。
症状やサイン
- 頻繁な嘔吐、特に毛玉の吐き戻し
- 便秘が続く
- 排便時に苦しそう
- 食欲不振
- お腹を触ると嫌がる
6. アレルギー性皮膚炎
秋に飛散するブタクサ・ヨモギといった花粉や、夏に繁殖したダニの死骸・フンがアレルゲンとなり、皮膚炎が悪化することがあります。
症状やサイン
- 身体を執拗に舐めたり噛んだりする
- 過剰なグルーミングで毛が薄くなっている
- 皮膚に赤みや小さなブツブツが見られる
- フケが増える
- 耳を頻繁に掻く、耳が赤く熱を持っている
7. 関節や古傷の痛み
秋の寒暖差や気圧の変化により体の血行が悪くなると、関節や古傷の痛みが悪化することがあります。
症状やサイン
- 高い場所へ飛び乗るのをためらう
- 寝起きや朝の動き、歩き方がぎこちない
- 体を触ると嫌がる
- 背中を丸めている
- 体が曲がりにくくなり、毛づくろいが雑になる。
猫の秋の病気を予防するには?飼い主ができる対策
秋に愛猫の病気を防ぐためには、猫の特性に合わせた自宅での対策が欠かせません。以下のようなケアを日常的に行えるといいですね。
1. 室内環境を整えて寒暖差と乾燥を防ぐ
秋の不調を引き起こす大きな原因が寒暖差と乾燥です。愛猫が過ごす部屋の環境を整えて、快適に過ごせるようにしてあげましょう。
・室内の温度を安定させる
寒暖差を感じずに済むように、エアコンなどを活用し、猫が過ごす部屋の温度を日中と夜間で大きく変えないように調整しましょう。
・湿度を保つ
空気の乾燥は、呼吸器系の粘膜や皮膚のバリア機能を弱めます。加湿器などを使って40~60%程度の湿度を保てるようにしましょう。洗濯物や濡れたタオルを干すのも効果的です。
・温かい寝床を用意する
冷えた床の上に寝続けないように、愛猫のお気に入りの場所に暖かいブランケットやドーム型のベッドを用意してあげましょう。好きなときに自由に行き来できるよう、複数箇所に設置してあげるのもいいですね。
2. 水分と栄養をしっかり摂らせる
秋に限った話ではありませんが、水分と栄養をしっかり摂ることは健康的な体づくりの基本です。特に秋は飲水量が減りやすいので、泌尿器や腎臓の病気を予防するためにも意識的に摂らせてあげましょう。
・水分補給を徹底する
水飲み場を複数用意したり、普段の食事にウェットフードを混ぜたりして、意識的に水分を摂らせてあげましょう。なかなか飲みたがらない場合は、水を少し温めてぬるま湯にすると飲みやすくなることがあります。
・消化に優しい食事を与える
消化器系の調子が悪い場合は、ウェットフードなど消化の良い食事を与えましょう。 食欲がないときは、いつものフードを少し温めて香りを立たせると食欲を刺激できます。
逆に食欲がありすぎるときは、食べすぎないようにフードの量を調整しましょう。
3. 体を外側からケアする
毛球症やアレルギーに対しては、外側からのケアが大切です。
・毎日ブラッシングする
抜け毛を飲み込んで毛球症や便秘になるのを防ぐために、換毛期は毎日丁寧にブラッシングしましょう。愛猫の嫌がらない範囲で優しく行ってください。
・アレルゲンを除去する
猫自身は外出しなくても、飼い主の服や窓から花粉やダニの胞子が持ち込まれてアレルギー症状が出ることがあります。猫が過ごす場所はこまめに掃除して、清潔に保ちましょう。
飼い主が外出した際は家に入る前に服に付着した花粉などを払い落とし、愛猫に触れる前に手を洗いましょう。
愛猫の健康に関する相談はオンラインでも
愛猫に体調不良や病気のサインが見られたら心配になりますが、通院を嫌がることも多いため、病院に連れていくべきか判断に迷うことがあるかもしれません。
そんなときは、ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話を通じて獣医師と繋がり、愛猫の様子を見せながら診察を受けることができます。獣医師が必要と判断した場合は薬も処方してもらえるため、困ったときは相談を検討してみてください。