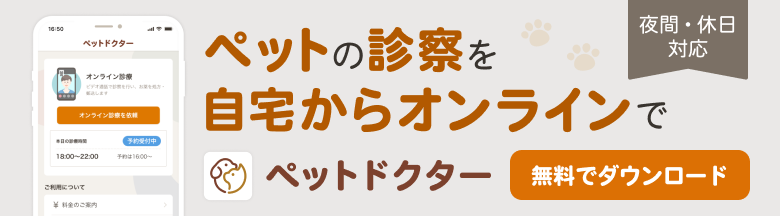2025年10月10日

暑い夏が終わり涼しくなり秋は、人にとっても猫にとっても過ごしやすいタイミングです。しかし夏の疲れや寒暖差などで体調を崩しやすかったり、寒くなってくることで事故の危険が多かったりするタイミングでもあります。そこでこの記事では、愛猫が秋を元気に過ごすために注意したい10個のポイントを解説します。
猫が秋に気をつけたいこと① 秋に発症しやすい病気
秋は夏の疲労の蓄積が表に出やすいタイミングです。また寒暖差が大きく、自律神経のバランスが乱れて免疫力が低下しやすかったり、空気の乾燥で喉や鼻の粘膜が弱りやすかったりする時期でもあります。このような様々な条件が重なることで、秋は以下のような不調が起こりやすくなります。
呼吸器系の病気(猫風邪など)
朝晩の冷え込みや乾燥で鼻や喉の粘膜が弱り、くしゃみ、鼻水、目ヤニの増加といった猫風邪の症状が出やすくなります。
消化器系の不調
自律神経の乱れや急な冷え込みでお腹を壊し、下痢や嘔吐が見られることがあります。
いずれの場合も、あとからご紹介する寒暖差対策や乾燥対策が予防や対策につながります。症状が続く場合は動物病院を受診しましょう。
猫が秋に気をつけたいこと② 秋のアレルギー
秋はブタクサやヨモギといった秋の花粉や、夏に繁殖したダニの死骸やフンといったアレルゲンが増加し、アレルギーが悪化しやすい時期です。
体を執拗に舐めたり噛んだりする、過剰なグルーミングで毛が薄くなる、皮膚に赤みやフケが見られるといった場合は、アレルギーでかゆみが出ている可能性があります。早めに動物病院を受診するようにしましょう。
猫が秋に気をつけたいこと③ 関節痛
特にシニア猫や持病を持つ猫は、寒暖差や気圧の変化で関節の痛みを感じやすくなります。
高い場所へ飛び乗るのをためらっていたり、体が曲げられずグルーミングが雑になったりしているときは、関節を痛がっている可能性があります。暖かい寝床を用意したりエアコンを使ったりして、体が冷えないようにしてあげましょう。症状が続く場合は動物病院を受診してください。
猫が秋に気をつけたいこと④ 寒暖差
秋は寒暖差が大きい季節です。寒暖差が大きくなると、体温を調節する自律神経に負荷がかかってバランスが乱れ、免疫力が低下したり、疲れやすくなったりします。
そのため室内の寒暖差を少なくすることが、秋を元気に過ごす鍵になります。エアコンなどを活用し、室内温度を日中と夜間で大きく変えないように安定させましょう。暖かいベッドやブランケット、カーペットを用意してあげるのもいいですね。
猫が秋に気をつけたいこと⑤ 乾燥
秋になると湿度が下がり、空気が乾燥します。空気が乾燥すると喉や気管支の粘膜が乾燥して風邪のリスクが高まるほか、皮膚のバリア機能が低下し、フケやかゆみが出やすくなります。暖房を使い始めるとさらに空気が乾燥するので、秋は加湿対策を行いましょう。
猫が快適に過ごせる湿度は一般的に40〜60%程度といわれています。加湿器を使用したり、濡れたタオルを室内に干したりして、快適な湿度を保ってくださいね。
猫が秋に気をつけたいこと⑥ 換毛期
猫の種類にもよりますが、秋は冬の寒さに備えて毛が生え変わるタイミングです。抜け毛が増えて新しい毛が生えてきます。
抜け毛が増える時期に注意が必要なのが、毛球症です。グルーミングで飲み込んだ大量の抜け毛が腸に詰まり、便秘や嘔吐といった消化器系のトラブルを引き起こします。
毛球症を予防するためには、こまめにブラッシングをして抜け毛を取り去ることが大切です。愛猫が嫌がらなければ毎日の日課にできるといいですね。
猫が秋に気をつけたいこと⑦ 水分補給
涼しくなると自然と水を飲む量が減ってしまいます。猫が水分不足になると、膀胱炎や尿結石といった泌尿器系のトラブルや、命にも関わる腎臓病のリスクが高まります。秋から冬にかけてはいつもより意識的に水を飲ませる工夫が必要です。
たとえば水飲み場の数を増やし、愛猫が立ち寄る場所やお気に入りの場所においてあげたり、普段の食事にウェットフードを混ぜたりしましょう。水を少しだけ温めてぬるま湯にすると、飲みやすくなることもあります。
猫が秋に気をつけたいこと⑧ 食べ過ぎ
秋は涼しくなって夏に落ちていた食欲が回復するうえに、冬に備えて食欲が増加する時期です。愛猫の食べる量が急に増えることがあるかもしれません。
適切に栄養を摂るのは大切なことですが、食べすぎると肥満につながり、関節に負担をかけたり、病気のリスクが高まったりします。また急な食事量の変化は消化器系にも負担をかけるので、一気に食べすぎないようにフードの量を調整しましょう。
猫が秋に気をつけたいこと⑨ 低温やけど
猫は寒さを感じると暖房器具に密着して動かなくなる習性があり、秋から冬は低温やけどのリスクが高まります。低温やけどは気づきにくく、いつのまにか皮膚の深い組織まで損傷してしまうことがあります。
ヒーターには必ずカバーや柵を設置し、愛猫が近づけないようにしてください。電気カーペットなどを使う際は低温にするほか、タイマー機能を使って長時間同じ場所で寝続けないように管理しましょう。
猫が秋に気をつけたいこと⑩ 台風や雷
秋は台風や悪天候が多く、猫が精神的なストレスを感じやすい時期です。例えば雷の大きな音や光、暴風の音などに恐怖を感じ、不安やパニックに陥って隠れたり過剰にグルーミングしたりすることがあります。
不安が強い場合は雨戸やカーテンを閉めて、外からの刺激をできるだけ少なくしてあげましょう。落ち着いて過ごせるハウスや段ボールを用意し、安心できる環境を整えてあげることも大切です。
猫の健康に関する相談はオンラインでも
秋は猫にちょっとした不調が現れやすいタイミングです。愛猫の様子がいつもと違うと心配になるものの、動物病院を受診するハードルが高く感じられることもあると思います。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話で獣医師と繋がり、外出することなく診察を受けることができます。獣医師が必要と判断した場合は薬も処方してもらえるので、心配なときは利用を検討してみてくださいね。