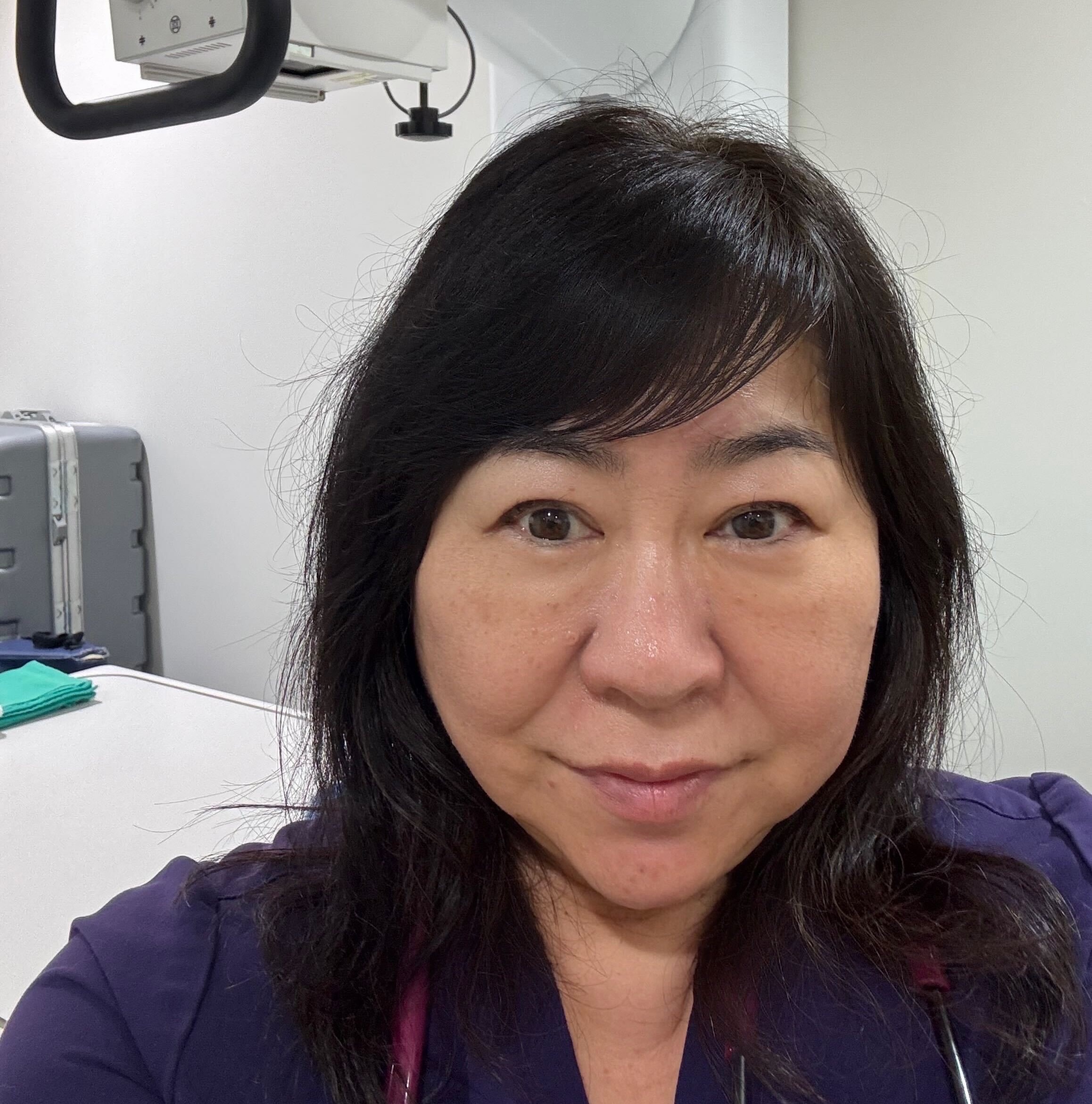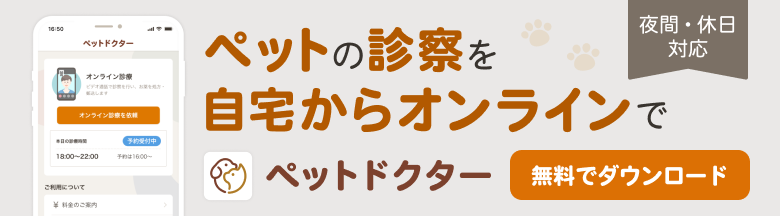2025年10月7日

季節の変わり目になると、なんとなく調子が悪いと感じる人も多いかもしれません。それは猫も同じで、様々な不調が現れることがあります。そこでこの記事では、季節の変わり目に猫に起こりやすい体調の変化や、できるだけ健康に過ごすために家庭でできる対策をご紹介します。
なぜ季節の変わり目は猫も体調を崩しやすい?寒暖差と気圧の変化に注意!
季節の変わり目に猫の調子が悪くなるのには、以下のような原因があります。
寒暖差と気圧の変化が引き起こす「自律神経の乱れ」
猫は人間のように体温を細かく調節するのが得意ではありません。そのため寒暖差が激しい環境にいると、体温調節を行う「自律神経」が、体温を一定に保とうとフル稼働します。急激な気圧の変化に対応するのも自律神経の役割なので、季節の変わり目は自律神経への負担が大きく、バランスが乱れがちです。
自律神経が乱れると内臓の働きが低下し、結果として免疫力の低下や消化器系の不調など、様々な体の不調につながります。これが季節の変わり目に「なんだか元気がない」「お腹を壊した」といった症状が見られる主な理由です。
夏の疲れも原因に
秋の場合は、夏の疲れが原因で体調を崩すこともあります。夏の間は、暑さから眠りが浅くなって睡眠不足になったり、食欲が落ちて栄養不足気味になったりしていることもあるでしょう。涼しくなったタイミングでこれらの蓄積された疲労が一気に表面化し、不調として現れることがあります。
季節の変わり目に猫に見られやすい不調や症状
季節の変わり目に猫に見られやすい不調には、以下のようなものがあります。猫は不調を隠すのが上手な動物です。不調のサインを見逃さないように、日頃から愛猫の様子を注意深く観察してあげましょう。
消化器系の不調
- 下痢や嘔吐:朝晩の冷え込みや寒暖差による自律神経への負担で、お腹の調子を崩して下痢や嘔吐をすることがあります。下痢や嘔吐の前に食欲がなくなるケースも多いです。
皮膚のトラブル
- 乾燥によるかゆみ:寒いと空気が乾燥し、猫の皮膚も乾燥しがちです。それによってフケが増えたり、体に痒みが出て頻繁に掻いたり噛んだりすることがあります。
- アレルギーの悪化:アトピーなどの持病を持つ猫は、季節の変わり目の気温や湿度の変化、花粉の影響などによって、アレルギー症状が悪化することがあります。この場合も掻く・噛むといった行動が見られるほか、皮膚が赤くなることもあります。
関節の不調
- 関節痛の悪化:シニア猫や、もともと関節に疾患を持つ猫は、朝晩の冷え込みで血行が悪くなり、痛みが強くなることがあります。触られることやグルーミングを嫌がったり、歩き方や姿勢がいつもと違ったりする場合は、関節が痛んでいる可能性があります。
呼吸器系の不調
- くしゃみや鼻水:自律神経が乱れて免疫力が低下すると、猫も風邪をひきやすくなります。くしゃみや鼻水などの症状が見られる場合は、風邪の可能性があります。
神経系の不調
- 神経系の病気:てんかんなど、神経系の病気を発症してしまうこともあります。特にてんかんなどの持病がある場合は注意が必要です。
精神系の不調
- 不安症:自律神経の乱れから、不安症がひどくなることがあります。季節の変わり目は天候が崩れることが多く、台風の風や雨の音、雷の音などで不安がひどくなり、眠れなくなることもあります。
季節の変わり目も愛猫に健康に過ごしてもらうために、飼い主ができる対策とは?
ここまでご説明した通り、季節の変わり目には様々な不調が出やすくなります。ここからは、愛猫にできるだけ健康に過ごしてもらうために、季節の変わり目に家庭で行いたいケア方法をご紹介します。
1. 室内の温度や湿度を管理する
寒暖差による自律神経の乱れを防ぐため、愛猫が過ごす場所の温度を26〜28℃程度に保ちましょう。暖房などをうまく活用してください。
ただし暖房を使うと空気が乾燥しがちです。40~60%程度の湿度に保てるように、加湿も行いましょう。加湿器を使用するほか、洗濯物や濡れたバスタオルなどを干すのも効果的です。
2. 寒い日は防寒対策をする
寒い日は防寒対策を行ってください。猫が好んで休む場所にブランケットを敷いたり、温かい寝床を用意したりしてあげるといいですね。ただし日中は暑い可能性もあるので、愛猫の様子を見ながら調整しましょう。
3. 免疫力を高める食事と水分補給をする
免疫力を高めるためには、日頃からバランスの取れた食事を摂ることが大切です。免疫力をサポートするタンパク質やビタミンといった栄養がバランスよく摂れるフードを食べさせてあげましょう。
また夏の疲れや寒さから水を飲む量が減ることもあるため、水分補給ができているかも確認してください。水分が不足すると脱水のおそれがあるだけでなく、尿路結石などの病気に繋がる恐れもあります。水飲み場を複数箇所に用意したり、ウェットフードを混ぜてあげたりして、水分補給を促せるといいですね。
4. 日々の健康チェックを欠かさない
先にもご説明した通り、猫は不調を隠そうとします。いつもより元気がない、あまり動かない、食欲がないなど、小さな変化を見逃さないためにも、日頃からしっかり様子を観察してあげてください。マッサージをしながら、関節の動き、皮膚の状態、毛のツヤなどをチェックする習慣もつけましょう。
いつもと違う様子が見られたり、気になることが出てきた場合には、早めに動物病院を受診して獣医師に相談すると安心です。
猫の健康に関する相談はオンラインでも
季節の変わり目に愛猫の「なんだかいつもと違う…」という様子に気づいても、猫を動物病院まで連れて行くのはハードルが高く、受診をためらったり、迷ったりすることもあるかもしれません。
そんなときは、ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅にいながらビデオ通話で獣医師の診察を受けることができます。獣医師が必要と判断した場合は薬も処方してもらえるので、困ったときは一人で抱え込まず、プロに相談することも検討してくださいね。