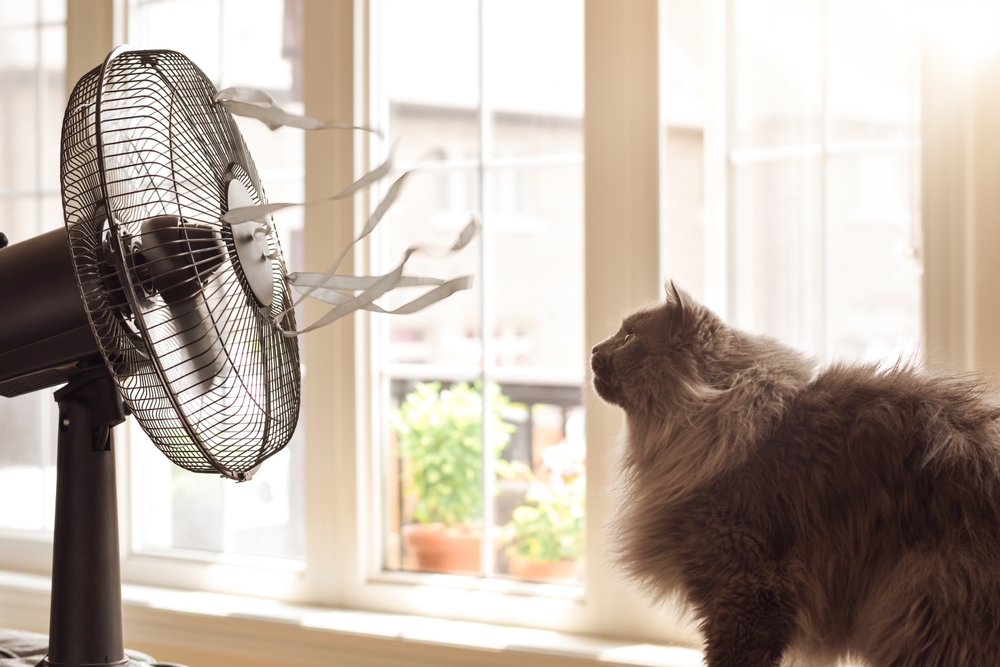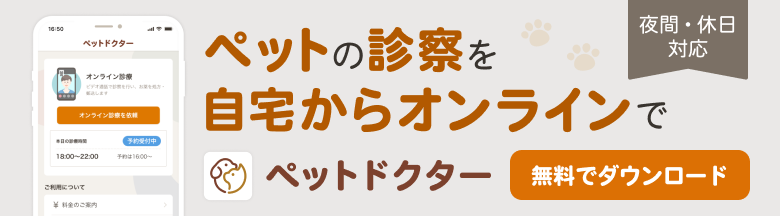2025年8月13日

夏になって、愛犬がいつもより元気がない気がする…というときは、もしかしたら夏バテかもしれません。この記事では犬の夏バテの症状やケア方法、夏バテしないための対策などをご紹介します。
夏バテとは?犬もなるの?
夏バテとは、夏の暑さによって引き起こされる様々な症状のことを指します。犬は体温調節が苦手で暑さに弱い生き物なので、高温多湿の季節になると人間と同じように夏バテすることがあります。
特に夏バテしやすい犬種や特徴
どの犬でも夏バテに注意が必要ですが、以下のような犬種や特徴を持つ犬は特に暑さに弱く、注意が必要です。
短頭種
犬は暑くなると「ハッハッ」と短く呼吸をすることで熱を体外に逃がし、体温を調整します(パディング)。しかし鼻が短くて気道が狭い短頭種の犬は、他の犬に比べて呼吸がしづらく、熱を外に逃がすのが苦手です。フレンチブルドックやパグ、シーズー、ボストンテリアなどは特に注意しましょう。
寒冷地方出身の犬
シベリアンハスキーやグレートピレニーズ、ボルゾイといった寒い地方で生まれた犬は、厳しい寒さに耐えられるよう、熱を溜めこむ分厚い毛で覆われています。そのため夏になると熱がこもりすぎて、ぐったりしてしまうことがあります。
毛が厚い犬種
柴犬やポメラニアン、シーズーといった毛が厚い犬(ダブルコートの犬)は、その厚い被毛によって体温が外に逃げづらく、暑さに弱いです。
子犬やシニア犬
子犬は体温調節機能が発達途中のため未熟で、逆にシニア犬は機能が低下しています。体の熱を上手に外に逃がすことができず、夏バテしやすいです。
特定の病気を抱えている犬
心臓病や呼吸器系の病気を抱えている犬は体温調節機能が低下しているため、夏バテしやすいです。加齢や持病の影響で体力が少ない犬も注意が必要です。
犬の夏バテの症状や兆候は?
犬が夏バテになると、一般的に次のような症状があらわれます。
いつもより元気がない、だるそう
夏にぐったりしていたり、元気がなくて遊びたがらなかったりするときは、夏バテを疑いましょう。犬は症状を言葉で伝えることができないので、「何となくいつもと違う」という飼い主の気付きが大切です。
落ち着きがない
落ち着きがなくうろうろしたり、不安そうにしたりしているときも、夏バテの可能性があります。
散歩に行きたがらない
夏バテしていると体がだるく動くのが億劫になるので、散歩好きの犬でも散歩を嫌がることがあります。
食欲がなくなる
夏にご飯を残すようになったり、おやつを欲しがらなくなったりするときは、夏バテの可能性があります。ただし食欲がなくなるのは他の病気の症状の可能性もあるので、夏バテだと決めつけず慎重に見守ることが大切です。
お腹がゆるい、便秘
夏バテすると胃腸に不調が現れることもあります。夏にいつもより便の回数が多い、下痢や軟便が続く、逆にいつもより便の回数が少なく便秘になる、という場合は、夏バテの可能性があります。
寝る時間が長くなる
夏バテで体がだるいと、いつもより長く寝るようになります。いつも起きている時間に寝ていたり、すぐに寝たがったりする場合は、夏バテを疑いましょう。
犬の夏バテで受診する目安は?
いつもより元気がない程度であれば、この後ご紹介するケアを自宅で行いながら様子を見てもいいでしょう。数日で元気になればそこまで心配する必要はありません。ケアをしても夏バテの症状が数日続くようであれば、一度病院で診てもらうと安心です。
ただし以下のような症状がある場合は、熱中症を起こしている可能性があります。速やかに病院を受診しましょう。
- パンティング(ハッハッという激しい口呼吸)が通常より激しい
- 心拍数が早い
- 体が熱い
- 体温が高い
- 口の中や舌が赤い
- 目が充血している
- よだれが多い
- フラフラしている
- 口の中や舌が青紫色(チアノーゼ)
- 嘔吐や下痢
- 体温が下がる
- ふるえ、痙攣
- 意識がない
犬の夏バテの対処方法は?
犬に夏バテのような様子が見られるときは、次のような方法でケアしてあげましょう。
できるだけ涼しいところで過ごさせる
ケージやお気に入りのクッションなど、愛犬が過ごす場所を冷房の効いた涼しい場所に移動してあげましょう。直射日光が当たらない日陰にしてください。ひんやりとしたタイルや大理石、冷却シートなどを敷いてあげるのもいいでしょう。
無理に散歩に行かない
元気がないときは、無理に散歩に行く必要はありません。室内でゆっくり休ませてあげましょう。
散歩に行きたがる場合は、早朝や夜間などの比較的涼しくてアスファルトが熱くない時間帯に行きましょう。いつもより短時間で済ませ、しっかり水分補給させてください。
消化がよく食べやすい食事を与える
夏バテのときは、水を多く含んで消化の良いウェットフードを与えましょう。いつも食べているドライフードをお湯でふやかすのも良いですね。食欲がないときは出汁や肉スープを加えて食べやすくしてあげるのもおすすめです。
病院を受診する
自宅で休ませてもなかなか回復しないときは、病院を受診しましょう。病気が隠れていないかの検査や点滴処置をしてもらえます。
犬の夏バテを予防するために家庭でできる対策5選
先にご説明した通り犬は暑さに弱いので、夏バテしないように日頃からしっかり対策をしてあげましょう。暑い季節は、以下の対策を心がけてください。
室内を過ごしやくする
犬が快適に過ごせる温度は一般的に25~28度程度です。犬種や年齢などによって異なるので、愛犬の様子を観察しながらちょうどよい室温に調整してあげましょう。お留守番のときや寝るときも冷房をつけておき、快適な室温が保てるようにしてください。
また強い日差しが入る部屋はカーテンや日よけを使ったり、冷却シートを敷いてあげるたりと、涼しく過ごせるように工夫してあげましょう。
散歩は涼しい時間にする
夏の散歩は早朝や夜間など、比較的涼しい時間帯にするようにしましょう。日が落ちてすぐなどはアスファルトが熱い可能性があるので、散歩に行く前に飼い主が手でアスファルトに触れて、愛犬が歩ける温度かを確認してください。
涼しい時間の散歩が難しい場合は、毎日無理に散歩させる必要はありません。そのぶん室内で体を動かせるよう工夫してあげましょう。
バランスのいい食事を与える
日頃から、バランスがよく愛犬の年齢や体調にあった食事を与えて、免疫力を高めておきましょう。愛犬が喜ぶからとおやつばかりを与えるのはNGですが、食べたくなるような好みのフードを選んでしっかり食べる習慣をつけることも大切です。
しっかり水分補給させる
日頃からしっかり水分補給させてあげましょう。新鮮な水をいつでも飲めるように、水飲み場にはいつもたっぷりの水をいれておいて、こまめに交換してください。留守番中にこぼしたりすると危険なので、水飲み場を複数用意するなどの工夫も大切です。
水をあまり飲みたがらない場合は、ウェットフードを混ぜたりドライフードをお湯でふやかしたりして、食事から水分を摂らせるのもいいでしょう。
こまめにブラッシングする
こまめにブラッシングして、抜け毛や毛玉を取り除いてあげましょう。犬の毛は熱を溜め込んでしまうので、不要な毛がなくなるだけでも体温の上昇を防ぐことができます。毛をカットするのもいいですが、短く切りすぎると逆に日差しや紫外線のダメージを受けやすくなる危険性もあります。極端に短くするのは避けてください。
犬の夏バテの相談はオンラインでも
愛犬に元気がないと、病院を受診した方が良いのか悩みますよね。しかし病院が遠かったり時間外だったりと、受診のハードルが高いこともあると思います。そんなときはオンライン診療サービス「ペットドクター」が便利です。自宅からオンラインで獣医師の診察を受けることができますよ。全国どこからでも利用できるので、困ったときは検討してみてください。