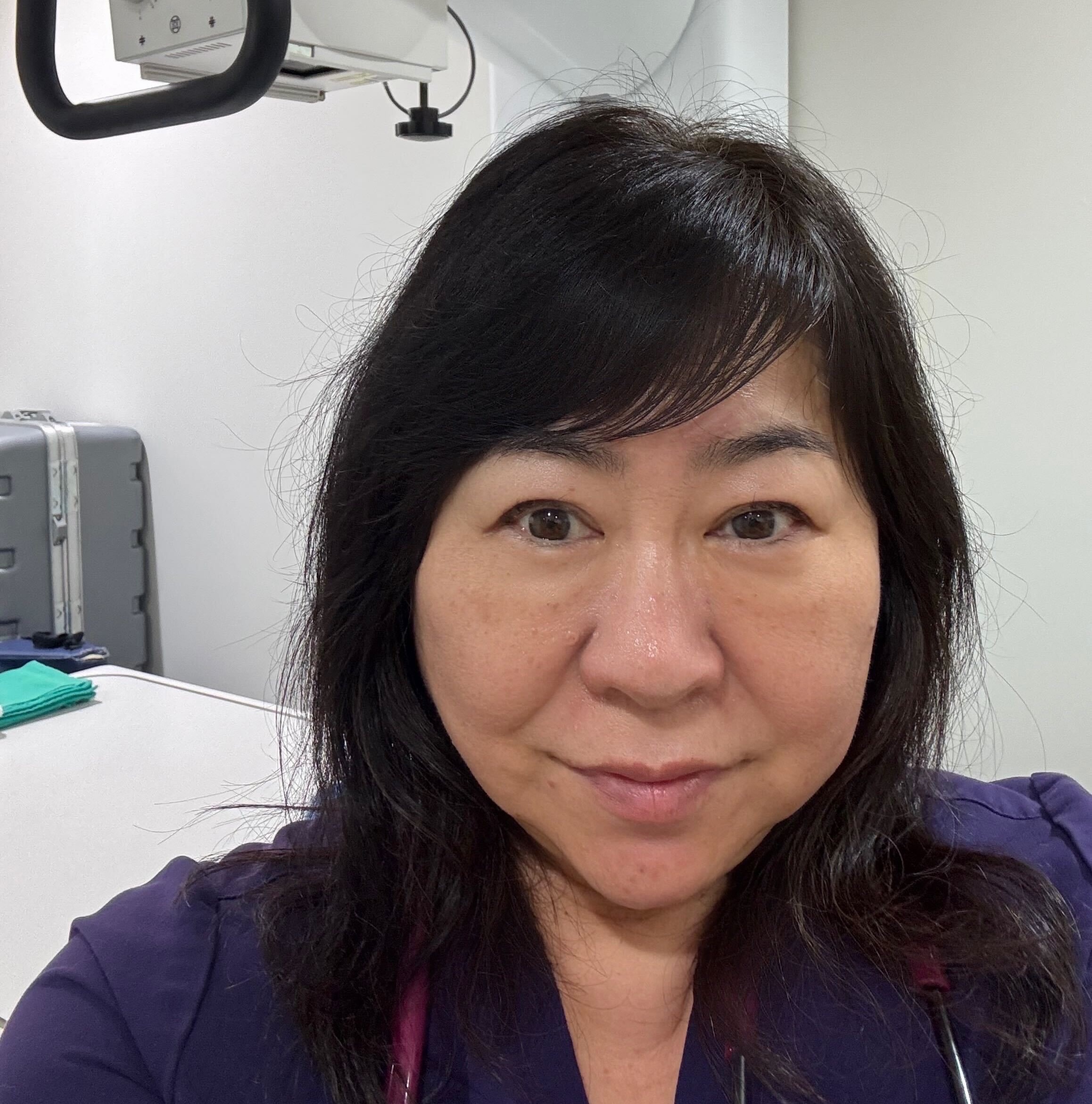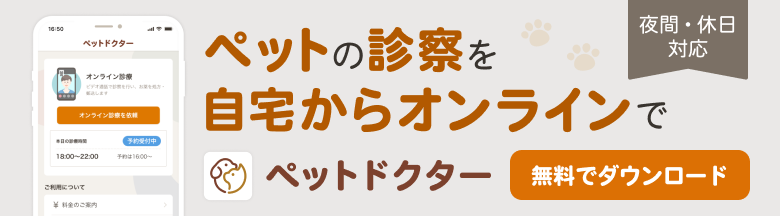2025年8月15日

愛猫の耳掃除は必要なのか、必要であれば頻度や正しい方法など、悩むことがあるかもしれませんね。こちらの記事では、猫の耳掃除の方法や頻度、注意点などをまとめました。ケアの際にぜひ参考にしてみてくださいね。
猫の耳掃除は必要?自宅でできるの?
猫の耳には、耳垢が外側に自然と出てくる自浄作用が備わっているため、耳の奥の方から耳垢を取り除くような耳掃除をする必要がありません。
ただ、耳の中を定期的にチェックし、汚れが気になるときだけ軽く拭き取る程度の耳掃除は自宅でできるといいでしょう。
猫の耳掃除の頻度は?
耳にトラブルや汚れがないかのチェックは、1週間に1回を目安に行いましょう。
チェックや掃除の方法は次の章でご紹介します。
猫の耳掃除の方法は?
ここからは自宅で行う猫の耳掃除の方法をご紹介します。
①耳の汚れをチェックする
愛猫の耳を軽くめくり、内側の汚れやにおいをチェックします。いつもと違う点がないか確認しましょう。耳の内側の溝に少し汚れがついているくらいなら、健康に問題はありません。
②コットンやガーゼ、ウェットシートで軽く拭く
汚れがある場合は、水や洗浄液(イヤークリーナー)で湿らせたコットンやガーゼ、ペット用のウェットシートで、目で見える部分の汚れだけを優しく撫でるように拭き取ります。
猫の耳掃除でやってはいけないことは?
猫の耳はデリケートなので、耳のケアは慎重に行う必要があります。ここでは、猫の耳掃除でやってはいけないポイントをご紹介します。
無理やり耳掃除をする
愛猫が嫌がっているのに力づくで耳掃除をするのはやめましょう。ケガにつながるので危険です。また耳掃除を嫌なものだと捉えてしまい、必要な耳のケアや治療がしづらくなる可能性があります。
嫌がるときは無理をせず、リラックスしているタイミングを見て少しずつ行うようにしてください。
綿棒を使う
綿棒を使って耳の奥まで掃除をすると、耳の中を傷つけてしまう可能性があるほか、汚れを逆に奥に押し込んでしまうことがあるため、使わないようにしましょう。
耳の奥まで掃除する
コットンやガーゼなどで汚れを拭き取る際に、耳の奥の方まで指を入れるのはやめましょう。耳が傷つくおそれがありますし、痛みや恐怖を感じて耳掃除がトラウマとなる可能性があります。
強く擦る
猫の耳はデリケートなので、コットンやガーゼで拭き取る際はゴシゴシ強く擦らないようにしましょう。汚れがこびりついてなかなか取れない場合は、新しいコットンやガーゼを用意して再度優しく拭いてあげてください。
汚れを一度にすべて取りきる必要はないので、後日改めて掃除してもいいでしょう。
猫が耳掃除を嫌がるときはどうする?
いざ耳掃除をしようとしても愛猫が嫌がってなかなかケアさせてくれない場合は、下記のようなことを意識してみてください。
耳を触ることに慣れさせる
耳を無理に触って警戒心を持たせてしまうと、その後のケアが難しくなります。普段からスキンシップの一環として耳を触ることに慣れさせ、耳を触ってもできるだけリラックス状態が保てるようにできると良いでしょう。
プロに任せる
愛猫が暴れるなどして自宅での耳掃除が難しい場合は、無理をせずプロに任せるのも一つの方法です。気になるときは動物病院で相談するか、トリミングのついでに、トリミングサロンで相談してみるのもいいでしょう。
特に外耳炎など耳に異常があるときは、耳掃除を嫌がるかもしれません。耳の皮膚が炎症を起こし、イヤークリーナーがしみて我慢できないこともあります。愛猫が異常に耳掃除を嫌がる場合は動物病院に連れて行き、獣医師に相談しましょう。
猫の耳掃除でわかる病気の兆候
耳をチェックした際に下記のような様子が見られる場合は、体調不良や病気などのトラブルが起こっている可能性があります。一度動物病院で診てもらうと安心です。
- 耳垢の量がいつもよりも多い
- 耳の中が臭い
- 黄色くドロっとした耳垢が出る
- 耳の中が黒ずんでいる
- しきりに耳を掻く
- 耳に傷やかさぶたがある
- フケが出ている
猫の耳のトラブルは、オンラインでも相談できます
愛猫の耳にトラブルがあるとき、獣医師に診てもらいたくてもすぐに病院に連れて行くのが難しいこともあるかと思います。そんなときはペットのオンライン診療サービス「ペットドクター」が便利です。家にいながらスマホの画面で獣医師の診察を受け、治療の必要性やホームケアの方法などを相談することが可能です。困ったときは利用を検討してみてくださいね。