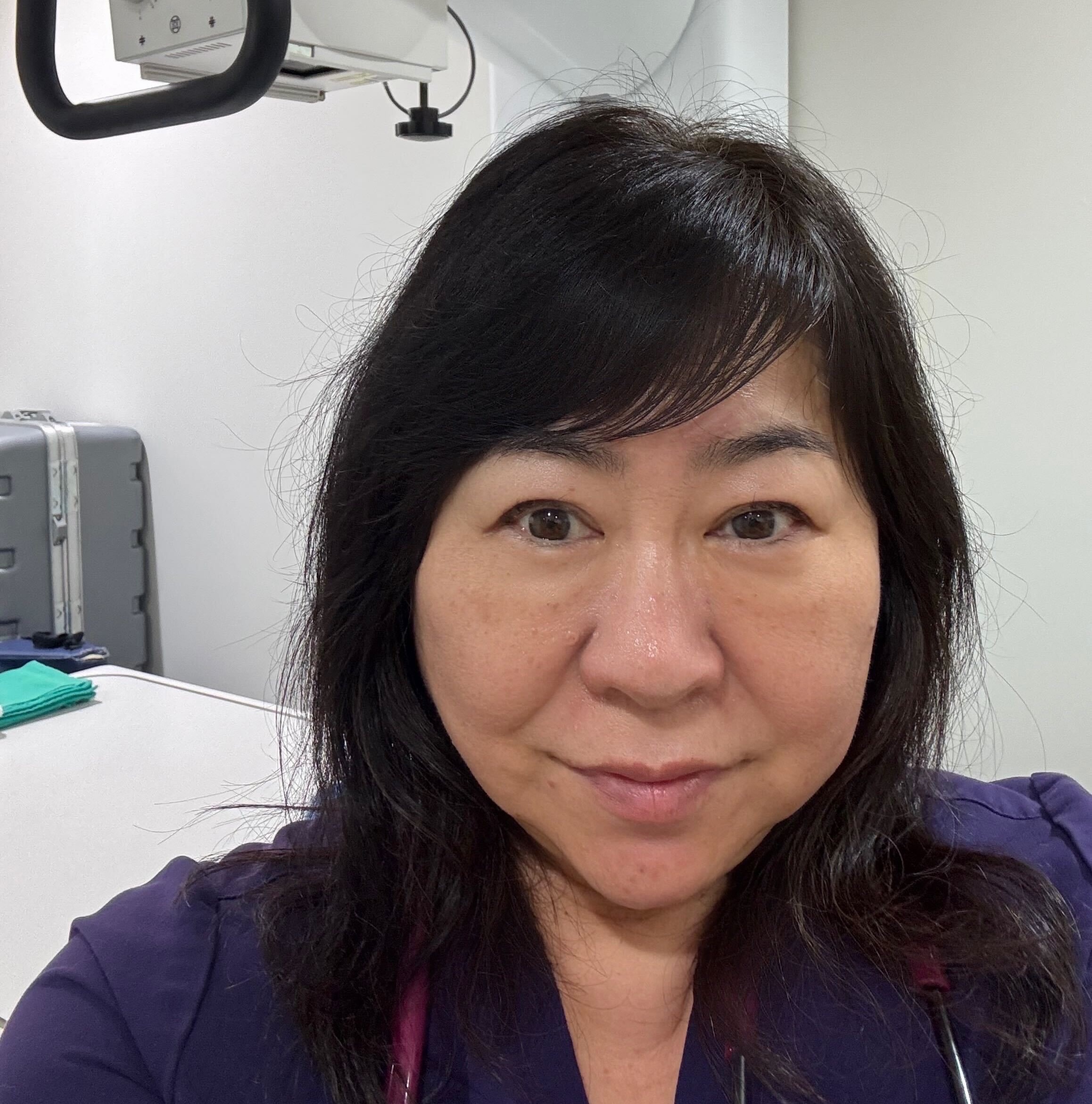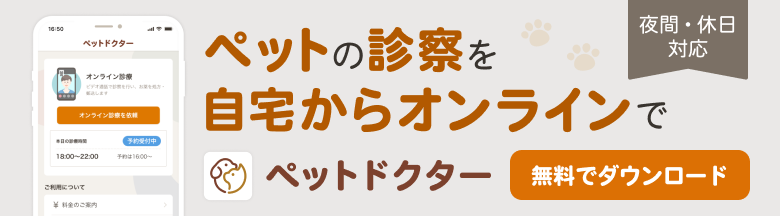2025年8月15日

愛犬の耳掃除について、定期的にした方が良いのか、掃除の方法や気をつけることなど、日常のケアで疑問に思うことがあるかと思います。こちらの記事では、犬の耳掃除の方法や頻度、やってはいけないことなどをご紹介します。
犬の耳掃除は必要?自宅でできるの?
犬の耳には自浄作用があり、奥にある耳垢は自然と外に出てくるようになっています。そのため基本的には、耳の奥にある耳垢を取り除くための耳掃除はする必要がありません。
自宅で定期的に行う必要があるのは、耳の中でトラブルが起こっていないかのチェックと、自浄作用によって出てきた汚れを優しく拭き取るケアです。
ただしアメリカンコッカースパニエルやシーズー、ラブラドールレトリバーなどの耳垢が溜まりやすい犬種や、耳の中をチェックした際に耳垢の量が多い場合、外耳炎などの耳のトラブルがあり自宅での耳掃除を指示された場合は、自宅で耳垢を取り除く耳掃除を行う必要があります。
犬の耳掃除の頻度は?
犬種や耳の汚れやすさにもよりますが、耳のチェックは1週間に1回は行うのが良いでしょう。過去に外耳炎に罹患したことがある場合は、外耳炎を繰り返すことが多いため、1週間に2~3回チェックするのがおすすめです。
チェックするのは、耳垢の量やにおい、色などです。自浄作用によって出てきた耳垢を拭き取るケアも、このときに行いましょう。
耳の奥にある耳垢を取り除く耳掃除が必要な場合は、2週間に1回を目安に行います。
犬の耳掃除の方法は?
ここからは自宅で行う犬の耳掃除の方法を、自浄作用で出てきた耳垢をケアする場合と、耳垢を取り除くためにしっかり耳掃除をする場合の2パターンに分けてご紹介します。
自浄作用で出てきた耳垢を掃除する方法
耳の中をチェックして耳垢の量や質感に異常がなければ、耳の内側の目に見える範囲の汚れだけを、犬専用の耳洗浄液(イヤークリーナー)を染み込ませたガーゼやコットンで拭き取ります。
このとき、必ずイヤークリーナーで湿らせたガーゼやコットンを使ってください。犬の耳の皮膚はとてもデリケートなので、乾いたガーゼやコットンで拭きとると傷をつけ、逆に外耳炎の原因を作ってしまいます。
また拭くときはゴシゴシ擦るのではなく、ガーゼやコットンを優しく押し当て、汚れを馴染ませてから優しく拭き取るようにしましょう。
耳の奥にある耳垢を取り除く耳掃除の方法
耳垢の量が多い犬種や、外耳炎などの耳のトラブルがあって自宅での耳掃除を指示された場合は、下記のような手順で耳掃除をしましょう。
① 愛犬が動かないようにする
愛犬を耳の穴が上になるような体勢にさせて、顔が動かないように抑えます。
② 洗浄液を耳に入れる
耳を軽く引っ張りながら、耳の穴に専用の洗浄液(イヤークリーナー)を入れます。耳の穴から液面が見えるくらいたっぷりと入れるようにしてください。
③ 耳をマッサージする
耳の付け根部分のコリコリとした部分を外側から指でつまむようにして、優しくゆっくりとマッサージします。耳の中の洗浄液のクチュクチュという音がすると、うまくマッサージができているサインです。
④ 愛犬に頭を振らせる
顔や体を抑えていた手を離すと犬がブルブル頭を振り、耳の中の洗浄液と溜まっていた汚れが出てきます。頭を振らない場合は、耳に息を吹きかけると振ることがあります。
このとき洗浄液や耳垢が床に飛び散ることがあるため、汚れても良い場所で行うようにしてください。
⑤ 耳についた汚れを拭き取る
洗浄液をつけたコットンやガーゼで、耳の入り口に出てきた汚れを優しく拭き取ります。
犬の耳掃除でやってはいけないこと
犬の耳はとてもデリケートです。掃除やケアは慎重に行いましょう。ここでは犬の耳掃除でやってはいけないポイントをご紹介します。
綿棒を使う
綿棒を使うと耳垢を奥に押し込んでしまい、逆に汚れが溜まって外耳炎の原因になる可能性があります。またデリケートな犬の耳を傷つける可能性もあるため、綿棒は使わないようにしましょう。
頻繁に耳掃除をする
先にもご説明した通り、犬に頻繁な耳掃除は必要ありません。過度な耳掃除はデリケートな耳を傷つけやすく、トラブルの原因になることがあるため、頻度の目安を守って掃除しましょう。
強く擦る
犬の耳はデリケートで傷つきやすいため、ガーゼやコットンでゴシゴシ擦るのはやめましょう。
アルコールの含まれたウェットティッシュを使う
アルコールの含まれたウェットティッシュは、耳の皮膚トラブルの原因になる可能性があるため避けた方が良いでしょう。
犬が耳掃除を嫌がるときはどうする?
愛犬が耳掃除を嫌がるときは次のような方法を試してみましょう。
耳を触れることに慣れさせてから掃除する
犬はいきなり耳を触られると嫌がることがあります。抱っこして撫でながらリラックスさせ、少しずつ顔周りや耳を触り、落ち着いた状態で耳掃除をするようにしましょう。
ご褒美をあげる
耳掃除を頑張ったらおやつをあげる、たくさん褒めてあげるなどご褒美をあげると、耳掃除をしやすくなることがあります。
プロに任せる
自宅での耳掃除が難しい場合は無理やり掃除せず、動物病院で獣医師に相談したり、トリミングのオプションにつけたりと、プロに任せましょう。自宅で無理やり掃除すると、耳の中を傷つけるなどしてトラブルにつながるおそれもあります。
プロに方法やコツを教わり、徐々に自宅でもできるようになると良いですね。
犬の耳掃除でわかる病気の兆候
犬の耳をチェックすることは、病気の兆候を見つけるきっかけにもなります。健康な場合、犬の耳垢は黄色みがかった白色で、においやベタつきはありません。
逆に耳をチェックしたときに下記のような様子があるときは、病気が隠れている可能性があります。動物病院で診てもらうのが良いでしょう。
黄色いドロっとした耳垢が見られる
黄色いドロっとした耳垢が見られる場合は、耳の皮膚が細菌に感染している可能性があります。症状が進行すると耳から膿が出る場合もあり、耳垢の色と膿のにおいで気づくこともあります。強いかゆみや痛みを伴うのが特徴です。
放置すると外耳炎から中耳炎、内耳炎へと進行し、悪化して首が片方に傾いたり同じ方向に回ったりという行動が見られることがあります。
茶色くベタついた耳垢が見られる
カビの一種であるマラセチアが増え、外耳炎が起こっている可能性があります。
茶色い耳垢の他に、頭を頻繁に振る、耳を掻くなど痒みを訴える行動が見られることがあります。
赤黒い耳垢が多く見られる
ミミダニ症に感染している可能性があります。強いかゆみを伴うのが特徴です。
完治させするには数回の治療が必要なため、早めに受診しましょう。
犬の耳のトラブルは、オンラインでも相談できます
犬が耳を掻いていたり耳の中が汚れていたりすると、大丈夫なのか心配になりますよね。 自宅でケアできるものなのか、病院で診てもらった方が良いのか、判断に悩むこともあるかと思います。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。家にいながらスマホのアプリで獣医師に症状を診てもらうことができます。自宅でケアできる場合は、ケアの方法を相談することも可能です。困ったときは利用を検討してみてくださいね。