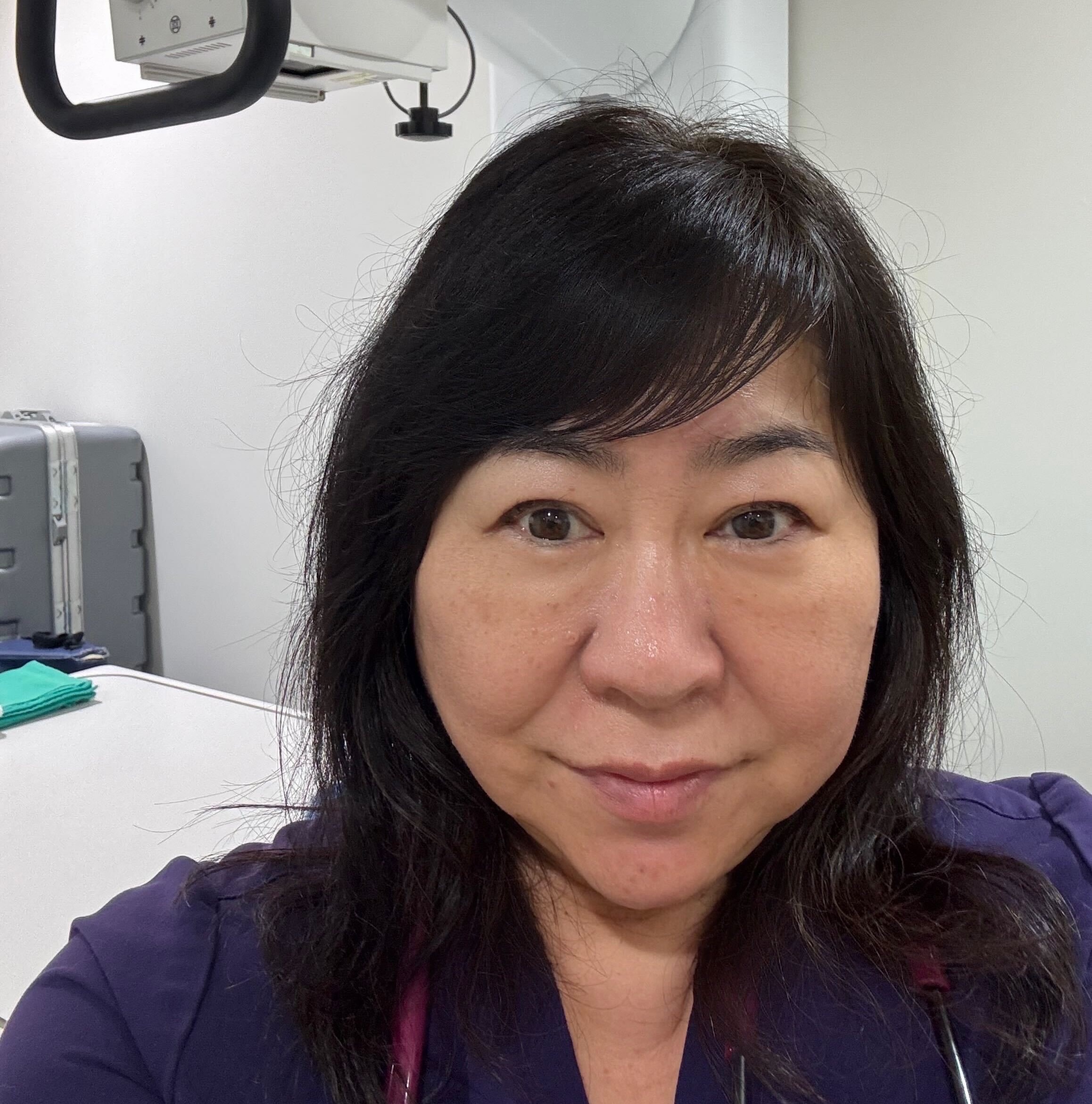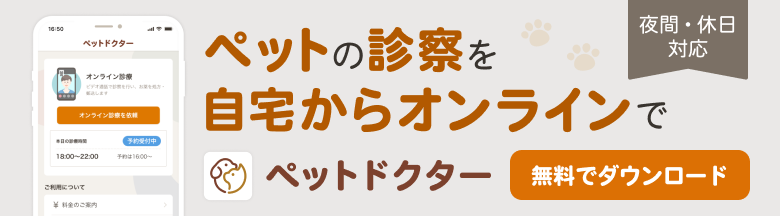2025年8月15日

愛犬の耳からいつもと違うにおいがすると、原因やケアの方法、受診した方が良いのかなど気になるかと思います。こちらの記事では、愛犬の耳が臭い原因や受診の目安、においの予防方法などをご紹介します。
犬の耳が臭い原因は?病気なの?
愛犬の耳が臭いと感じる場合、耳の中で炎症が起こり、外耳炎や中耳炎になっている可能性があります。炎症は下記のような原因で起こります。
細菌や真菌の感染
細菌や真菌は健康な犬の耳や皮膚にも存在していますが、免疫力が低下したり耳の皮膚の状態が悪くなったりすると、増殖して炎症を起こすことがあります。
耳ダニの寄生
耳ダニというダニが耳の中に寄生することによって炎症を起こし、耳が臭くなることがあります。においの他に黒い耳垢が大量に出るのが特徴です。
アレルギー
食物、ホコリ、ダニなどのアレルギーを持っていると、免疫のバランスが崩れ炎症を起こしやすくなり、においの原因になる場合があります。
異物の混入
耳の中に水が入ったり、散歩中に植物の種子や砂などの異物が入ると炎症を起こし、においの原因になります。
耳が臭くなりやすい犬種は?
どの犬も耳が臭くなることはありますが、以下のような犬種は特に耳が臭くなりやすいです。
垂れ耳の犬種
耳の中が蒸れて菌が繁殖しやすいため、耳が臭くなりやすいです。
- キャバリア
- ビーグル
- マルチーズ
- シーズー
- ダックスフンド
- コッカースパニエル
- バセットハウンド
- ボーダーコリー
- ゴールデンレトリーバー
- ラブラドールレトリーバー など
耳の中に毛が多い犬種
垂れ耳の犬と同じく耳の中が蒸れて菌が繁殖しやすく、耳が臭くなりやすい傾向にあります。
- トイプードル
- ミニチュアシュナウザー
- シーズー
- ヨークシャーテリア など
アレルギーになりやすい体質の犬種
皮膚のバリア機能が弱くて耳の炎症が起こりやすいため、耳が臭くなることがあります。
- パグ
- フレンチブルドッグ
- 柴犬 など
犬の耳が臭いときに病院を受診する目安は?
前述の通り、犬の耳が臭いときは耳の中で何らかのトラブルが起こっている可能性があるため、早めに病院を受診するようにしましょう。
できるだけ早期に受診することで、症状の悪化を防ぎ、治療期間を短くすることが期待できます。
犬の耳が臭いときの治療方法は?
愛犬の耳の臭いが気になって病院で受診すると、下記のような治療を行うことがあります。
耳の洗浄
まずは耳の洗浄を行うことがほとんどです。専用の洗浄液を使って、耳垢や寄生虫、異物などを取り除きます。このとき、耳の周りや中の毛を切ることもあります。
点耳薬や内服薬の投与
耳の中で炎症を起こしている場合、洗浄だけでは細菌や真菌を取り除ききれないことが多いため、抗菌薬や炎症を抑える薬、駆虫薬などを投与します。
点耳薬を使うことが多いですが、耳が腫れていて点耳薬が奥まで入りきらない場合や、鼓膜より奥で炎症が起こっている場合は、内服薬を使うこともあります。
手術での治療
外耳炎の症状が進行し、中耳炎や内耳炎になっている場合は、鼓膜を切開して洗浄する手術を行う場合があります。
アレルギーの治療
炎症の原因にアレルギーが疑われる場合は、アレルギー検査を行うことがあります。アレルゲンが特定できたら、フードの変更やハウスダスト対策などのアレルゲンを避ける対策をとります。
症状がなかなか改善しない場合は、症状を和らげるためにステロイド剤を使うことがあります。
犬の耳が臭いときに自宅でできるケア方法は?
犬の耳が臭いときは、自宅でも耳の中をできるだけ清潔に保つことが大切です。
できるだけ毎日耳の中の状態をチェックし、入り口付近についた汚れを、専用の洗浄液(イヤークリーナー)を染み込ませたコットンやガーゼで優しく拭き取るようにしましょう。
状態によっては、洗浄液を直接耳の中に入れる耳掃除や、点耳薬を入れるケアを自宅で行うよう獣医師から指示されることもあります。
犬の耳の臭いを予防する方法は?
愛犬の耳の臭いを予防するには、日頃から以下のようなケアをしてあげられると良いでしょう。
定期的に耳のチェックとケアを行う
耳の中でトラブルが起こっていないか確認するためにも、少なくとも1週間に1回程度は耳の中のチェックをしましょう。過去に外耳炎にかかったことがある場合や、何度も外耳炎を繰り返している場合は、1週間に2~3回チェックするのがいいでしょう。
耳垢の量や質、耳のにおい、色などにいつもと違うところがないか確認し、耳の入り口に汚れがある場合は、専用の洗浄液(イヤークリーナー)を染み込ませたコットンやガーゼで優しく拭き取ります。
耳のトラブルが起こりやすい犬種は、洗浄液を耳に入れて洗浄するケアが必要なこともあります。気になる場合は獣医師に相談してみてください。
耳の中を蒸れさせない
耳の中が蒸れると菌が繁殖してトラブルが起こりやすく、耳のにおいの原因になります。耳の中の毛が長い犬種の場合はトリミングサロンで短くカットしてもらう、シャンプーや水遊びの後は時間をかけて水分を拭き取りしっかり乾燥させるなどして、できるだけ耳の中の通気性を良く、湿度を低く保てると良いでしょう。
アレルギー対策を行う
食べ物やホコリ、ダニなどのアレルギーが原因で耳のトラブルが起こることもあります。ケアを行っても耳のトラブルを繰り返し、アレルギーが疑われる場合は、検査を受けて原因のアレルゲンを特定し、できるだけ避けられるようにすると良いでしょう。
犬の耳のトラブルはオンラインでも相談できます
犬の耳の様子がいつもと違うと、病気やトラブルがあるのではと気になりますよね。自分ではなかなか対応を判断できないこともあるかと思います。
そんなときはペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。家にいながらスマホのアプリで獣医師の診察を受け、適切な対応を相談することができます。困ったときは利用を検討してみてくださいね。