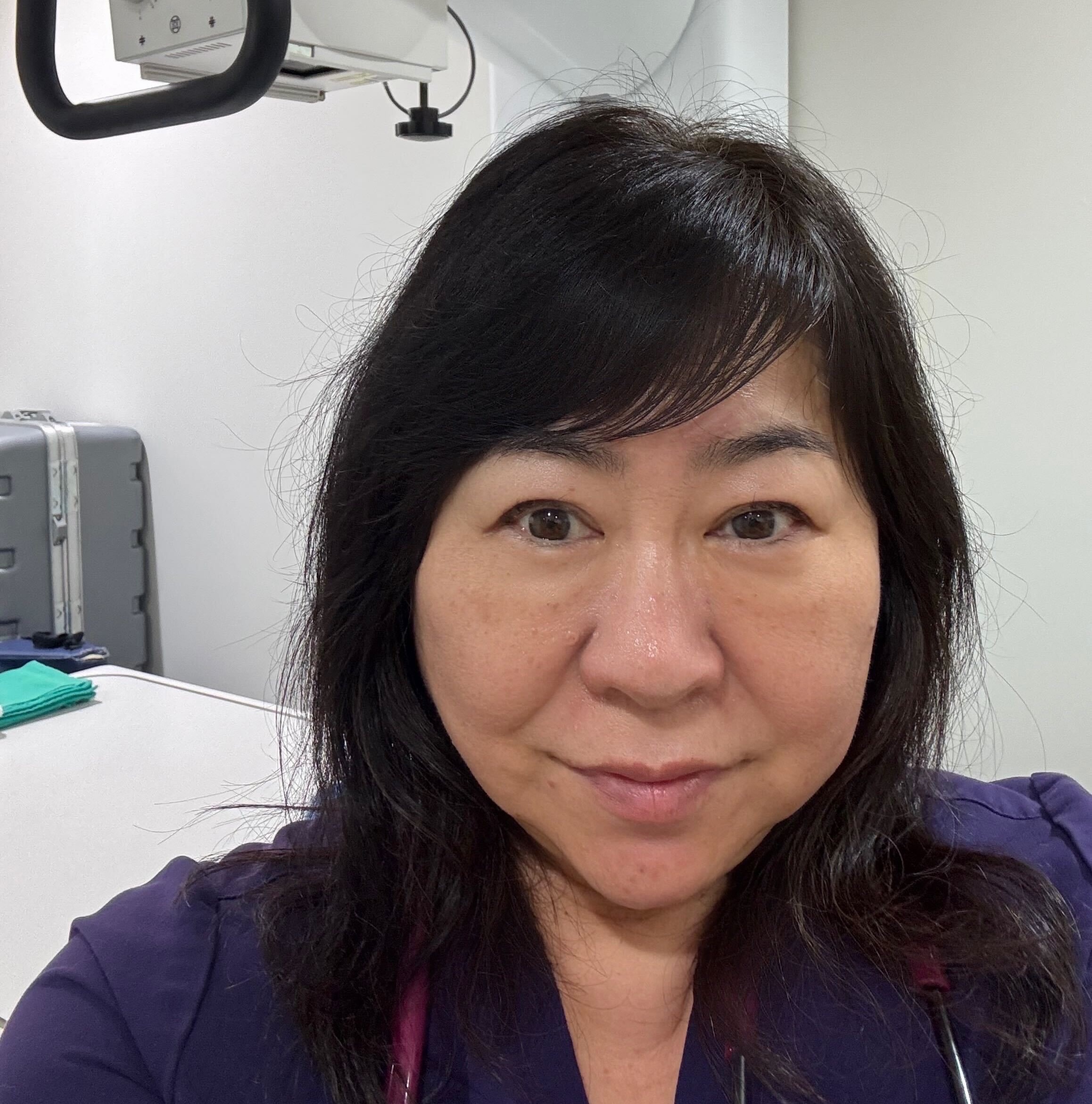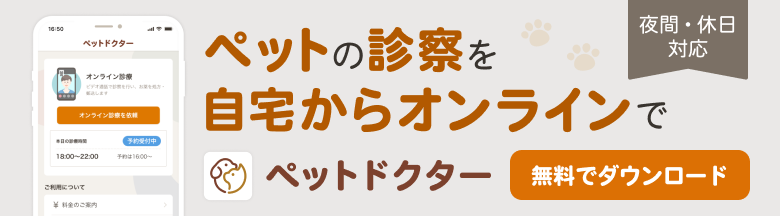2025年10月7日

秋や春などのいわゆる季節の変わり目には、人間と同じように犬も調子を崩しやすいことをご存知ですか?この記事では、季節の変わり目に犬に不調が現れやすい原因や、季節の変わり目も愛犬に元気に過ごしてもらうために飼い主ができるケア方法について解説します。
季節の変わり目は犬も体調を崩しやすい?寒暖差に注意!
季節の変わり目は、人間と同じように犬も体調を崩しやすいタイミングです。明らかな体調不良でなくても、なんとなく元気がなかったり、体を痒がったりすることもあります。
季節の変わり目に犬に不調が現れやすい主な原因には、以下のようなものがあります。
寒暖差
季節の変わり目は、寒暖差が大きくなりがちです。数日の間で気温が大きく変動することもありますし、朝晩は冷えるのに日中は暑いなど、1日の中でも大きな変化があります。
犬は人間に比べて体温を細かく調節する機能が発達していないため、急激な気温の変化が得意ではありません。体温調節を司る「自律神経」が、体温を一定に保とうとフル稼働することで大きな負担を受け、バランスを崩してしまいます。
自律神経のバランスが乱れると、免疫力の低下や消化器系の不調など、様々な体の不調につながります。
気圧の変化
季節の変わり目は、気圧の変動も激しくなります。気圧の変化に応じて体のバランスを保つのも、自律神経の仕事です。つまりここでも自律神経に大きな負担がかかり、様々な不調を引き起こします。
特に台風などで低気圧が近づくと、自律神経の乱れから体内の水分バランスが乱れたり、古傷や関節痛がある部分が痛んだりすることがあります。
夏の疲れ
秋の場合は、夏の疲れが原因で体調を崩すこともあります。暑い夏を乗り切るために、犬の体は知らず知らずのうちに大きな負担を抱えています。暑さから眠りが浅くなって睡眠不足になったり、食欲が落ちて栄養不足気味になったりしていることもあるでしょう。
その蓄積が秋になって表面化し、なんとなく元気がない、食欲がないといった不調として現れることがあります。
季節の変わり目に起こりやすい犬の不調
季節の変わり目に犬に見られる不調には、以下のようなものがあります。愛犬の様子を注意深く観察し、不調に早めに気づいてあげられるといいですね。
消化器系の不調
- 下痢や嘔吐:朝晩の冷え込みや寒暖差、生活リズムの変化による自律神経への負担で、お腹の調子を崩して下痢や嘔吐をすることがあります。
皮膚のトラブル
- 乾燥によるかゆみ:暖房を使うと空気が乾燥し、犬の皮膚も乾燥しがちです。それによってフケが増えたり、体を頻繁に掻くようになったりすることがあります。
- アレルギーの悪化:アトピーなどの持病を持つ犬は、季節の変わり目の気温や湿度の変化、花粉の飛散などによって、アレルギー症状が悪化することがあります。
関節の不調
- 関節痛の悪化:シニア犬や、もともと関節に疾患を持つ犬は、朝晩の冷え込みで血行が悪くなり、痛みが強くなることがあります。
呼吸器系の不調
- 風邪や咳:自律神経が乱れて免疫力が低下すると、犬も風邪をひきやすくなります。くしゃみや鼻水、咳などの症状が見られる場合は、風邪の可能性があります。
神経系の不調
- 神経系の病気:てんかんなど、神経系の病気を発症してしまうこともあります。神経系の持病がある場合は特に注意が必要です。
精神系の不調
- 不安症の悪化:自律神経の乱れにより、不安症など精神系の不調がひどくなることがあります。台風の風や雨の音、雷の音で不安がひどくなり、眠れなくなることもあります。
季節の変わり目に飼い主ができる対策とは?
ここまでご説明した通り、季節の変わり目は様々な不調が出やすいタイミングです。ある程度仕方ない部分もありますが、愛犬にはできるだけ元気に過ごしてほしいですよね。
そこでここからは、季節の変わり目に飼い主ができるケアをご紹介します。
1. 室内の温度や湿度を管理する
部屋の温度を一定に保つことで、寒暖差による自律神経の乱れを防ぐことができます。エアコンなどを使用し、愛犬が過ごす場所の温度を25〜28℃に保つことを目安にしましょう。
温度とあわせて、湿度の管理も大切です。特に暖房を使っていると乾燥しがちなので注意しましょう。犬が快適に過ごせる湿度は40~60%といわれています。加湿器を使用するほか、洗濯物や濡れたバスタオルなどを干し、部屋を加湿してください。
2. 散歩の時間帯を見直す
朝晩の冷え込みが厳しい日は、気温が比較的安定しているお昼頃に散歩に行くことを検討しましょう。寒暖差による疲れが軽減されます。
3. 寒い日は防寒対策をする
寒い日は防寒対策を行いましょう。お気に入りの場所にブランケットを敷いたり、服を着せたりしてあげてください。ただし日中は暑い可能性もあるので、愛犬の様子を見ながら調整しましょう。
4. 免疫力を高める食事と水分補給をする
免疫力を高めるためには、日頃からバランスの取れた食事が大切です。免疫力をサポートするタンパク質やビタミンといった栄養がバランスよく摂れるフードを、しっかり食べさせてあげましょう。
また 寒いと水を飲む量が減りがちです。水飲み場をを複数箇所に用意したり、ウェットフードを混ぜてあげたりして、水分補給を促しましょう。
5. 日々の健康チェックを欠かさない
いつもより元気がない、寝ている時間が増えた、食欲がないなど、小さな変化を見逃さないためにも、日頃からしっかり様子を観察してあげてください。ブラッシングやマッサージをしながら、関節の動き、皮膚の状態、毛のツヤなどをチェックする習慣もつけましょう。
いつもと違う様子が見られた場合は、早めに動物病院を受診すると安心です。
犬の健康に関する相談はオンラインでも
季節の変わり目に、愛犬の「なんだかいつもと違うな…」という様子に気づいても、動物病院に連れて行くのはハードルが高く、受診するか迷ってしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が便利です。自宅からビデオ通話で獣医師に愛犬の様子を見せ、相談することができます。獣医師が必要と判断したときは薬の処方も可能です。不安なことがあるときはぜひ検討してみてくださいね。